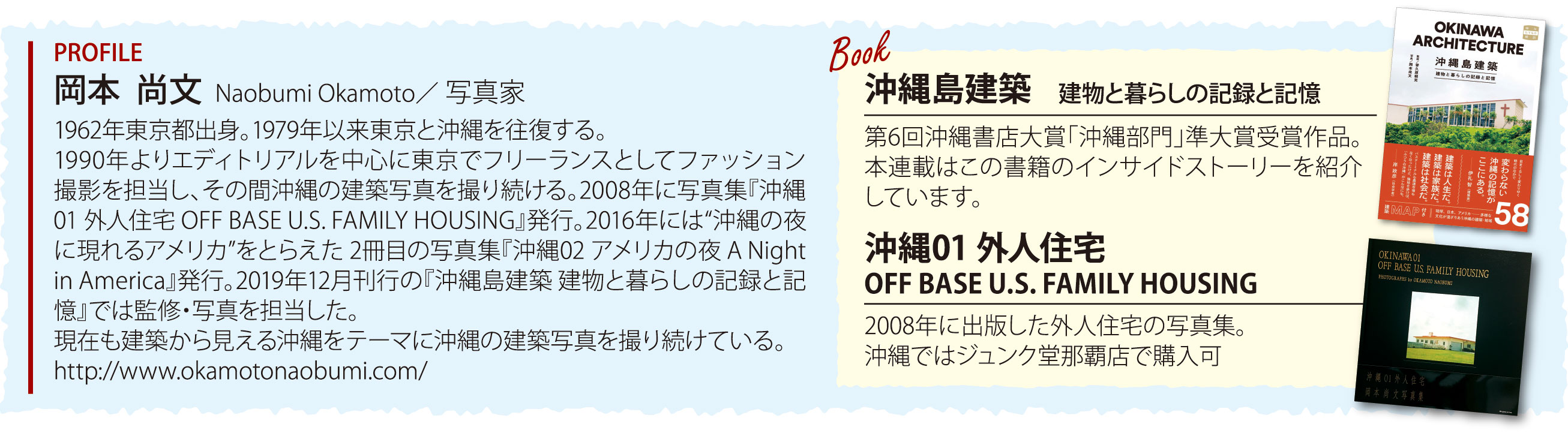沖縄島建築 インサイドストーリー Episode6 憧れと外人住宅

週刊かふう2020年10月16日号に掲載された内容です。
Episode6 憧れと外人住宅
建物を介して沖縄の歴史や文化、そして暮らしを見ていく「沖縄島建築 インサイドストーリー」連載第6回は「外人住宅」です。
外人住宅は、ほとんどが建てられてから50年以上が経過し、老朽化が進んでいますが、改装してレストランなどに使用されるなど、今でもそのスタイルを好んで使用し、暮らす人々が居ます。
まずはその成り立ちを見ていきましょう。
1945年、沖縄戦は終結しました。戦死者はおよそ20万人と言われています。
その後、沖縄は日本の独立の代償としてアメリカに提供され、米軍による軍事的支配が始まりました。
1946年4月には、沖縄民政府が設立されます。
1952年4月、サンフランシスコ講和条約と日米安全保障条約が発効され、日本は独立します。しかし、沖縄は日本から切り離され、その後日本に復帰する1972年まで米軍の施政権下におかれました。
1950年に始まる朝鮮戦争によって沖縄は「Key Stone of the Pacific(太平洋の要石)」として、冷戦下の軍事的拠点となります。
その後、1960年、ヴェトナム戦争が勃発。地理的にその戦略拠点となるなかで、基地は増強され、同時に軍人軍属およびその家族も増えて行きました。基地内の住宅施設ではそれらの人員を収容しきれなくなり、民間による外国人(アメリカ人)専用の賃貸住宅がフェンスのこちら側に建設されるようになりました。
こうした戦後沖縄の歴史の中で、外人住宅は必然的に誕生しました。
主に外人住宅は基地周辺に存在しました。その北端は石川市(現在のうるま市)、南端は佐敷町(南城市)でしたが、嘉手納や普天間などの大規模な基地を抱える中部を中心に多くの住宅が建設されました。
いわゆる、コンクリートスラブのフラットルーフ、鉄筋とコンクリートブロックを使用した基地外の外人住宅は1950年代後半から建造され、以後1970年代前半まで増えつづけました。
ごく初期のものはコンクリートスラブのフラットルーフではなく、鉄筋とコンクリートブロックの上に木造で組んだ赤瓦屋根が載っていました。これは今ではとても少なくなっていますが、沖縄市の高原や南城市馬天などに残っています。
軍の要請による外人住宅の建設には、土地建物の広さ、素材の選定や間取り、付帯設備などさまざまな条件が義務づけられ、沖縄の民間業者は米軍指導のもと、手探りで住宅建設を開始しました。
それはまさに見よう見まねで獲得した技術だったのです。
代表的な住宅は、一戸あたりの総面積が約300㎡。そこに100㎡前後の建物、エアコン付きの3ベッドルーム&リビング、キッチン&バス、それにユーティリティールームと呼ばれるメイド用の作業ルームが備わっており、それ以外の敷地は広々とした芝生のガーデンと駐車場として使用されました。
一方、沖縄住民に対しては、1950年に復金(琉球復興金融基金)の融資制度が始まり、住宅建設が急速に進みましたが、まだまだ木造セメント瓦や木造赤瓦住宅が主流でした。
それは、戦争によって何もかも失ったところからのスタートだったのです。
そのような暮らしの中で、フェンスの向こう側、基地内に建つ白いフラットハウスを沖縄の人々はどんな気持ちで眺めていたのでしょう。
そして、フェンスのこちら側に建てられ始めた外人住宅。
庭で行われるバーベキューやパーティー。クリスマスの飾り付け。初めてのアメリカ人との交流。
メイドやガーデンボーイは憧れの仕事だったと言います。
もちろんその関わりの中では、近隣とのトラブルや場合によっては悲しい出来事も少なくはなかったのかもしれません。
沖縄とアメリカ。
それは、沖縄の人々が自主的に選び取ったものではなく、戦争と占領によって言わば強制的に出会わされたものでした。
戦争が終わってからの長い時間の中、憧れと憎しみに折り合いをつけて逞しく生きた人々が作った「文化」が沖縄にはたくさんあります。
その「文化」のひとつとして、コンクリートスラブのフラットルーフ、鉄筋とコンクリートブロックを使用した外人住宅はあるのではないでしょうか。
海を望む斜面に建つ少々老朽化した外人住宅を眺めていると、そうした沖縄の姿が映って見えます。