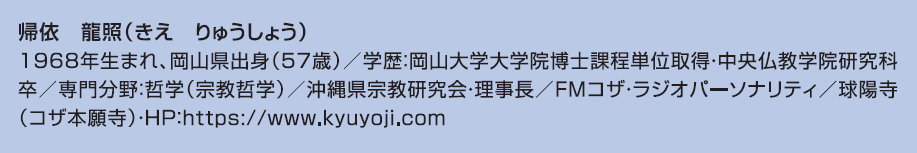琉球・沖縄年中行事 なんでもQ&A 知っていおきたい! トートーメーの専門用語②

週刊かふう2025年10月10日号に掲載された内容です。
トートーメーの『ウタチアギ(お焚き上げ)』
Q:先日、祖父の三回忌~三十三回忌をまとめて行いました。ユタのおばさんから、「法事も終わったし、もうトートーメーはいらないから燃やしなさい」と言われました。でも、焼却処分にはかなり抵抗があります。これって本当に沖縄のしきたりなのでしょうか?(嘉手納町・Tさん・40代)
A:昨今の沖縄では、県外からの影響もあり、併修(へいしゅう=併用の勤修)という、ご法事をまとめてお勤めするケースが増える傾向にあります。
以前の沖縄では、単修(たんしゅう=単用の勤修)という、ご法事をきちんと分けてお勤めすることが主流でしたが、これも時代の流れの一つなのでしょう。
賛否が分かれるポイントは、何回忌と何回忌のご法事を一緒にお勤めするかだと思います。とある方は、赤(紅)色のカマボコ同士だから二十五回忌と三十三回忌は一緒にできるとか、数字が二桁だから十三回忌~三十三回忌は一緒にできるとか、ミーサーアキ(喪明け)の三回忌は終わっているから七回忌~三十三回忌は一緒にできるとか、極端なケースでは、「初七日~三十三回忌まで、全部まとめてお経を読めますか?」と葬式の後の納骨のとき、驚くようなご質問をいただくことも……。「お互いの今日があるのは、どなたのお蔭さまなのでしょうか?」と、『ウヤファーフジ・ウヤヌグウン(ご先祖様・親のご恩)』を胸の内で問いたくなることもあります。
三十三回忌までお勤めしたのですから、お敬いする対象のトートーメーは、ユタの先生のお言葉をお借りすれば、「いらない」のでしょうが、沖縄では、併修してもグミーニチ(故人さまの毎年の命日)などには、ご家族・ご親族のお近しい方々は、きちんとお仏壇へティーウサー(合掌)・ウヌフェー(礼拝)することがほとんどです。
そのため、Tさんにはトートーメーを早急にウタチアギ(お焚き上げ)することなく、現状のまま大切にお仏壇へご安置して、お敬いを継続していただければと存じます。ちなみに、ウタチアギは別名、昇天供養ともいい、立派な沖縄のしきたりの一つだと言われています。
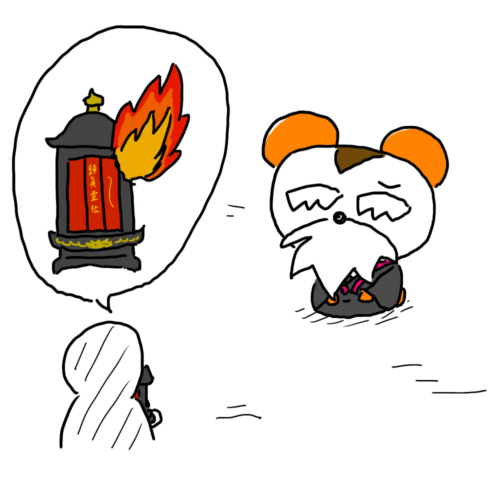
トートーメーの『フスクフダ(不足札)』
Q:我が家のトートーメーは、書いた人が下手くそで、まったく読めません。しかも、グソーの名前が表に書かれ、さらに読めません。裏には名前だけで苗字もないし、死んだ日や死んだ歳も書かれていません。明らかにウグヮンが不足ですよね?(南風原町・Sさん・60代)
A:トートーメーのお札の正面には、お葬式のシルイフェー(白木位牌)と同じく、法名・戒名という、仏名(仏さまのお名前)を書くことが正式です。しかし、沖縄では、クヮンマガー(子や孫)が読みやすいようにと、俗名(生前のお名前)を書くことも多くあります。
トートーメーのお札は、楷書(読みやすさを優先するするため)にて、仏式でお勤めの場合は仏名・俗名・死亡年月日・行年(享年・数え年)はもとより、続柄・屋号などを記載することもあり、記入漏れや誤字脱字を未然に防ぐ意味から、可能であれば、ご寺院・仏壇仏具店の専門家へご依頼することが賢明です。とはいえ、素人の方が記載されることも沖縄では多く、このように記入ミスのあるお札のことをフスクフダ(不足札)といいます。
しかし、沖縄のしきたりに詳しい先生方は、フスクフダを意図的に作られることもあります。一例では、離婚された娘さまが実家の苗字に復氏しない(苗字を戻さない)とき、あえて嫁ぎ先や実家の苗字を記載せず、下の名前のみを記載することが知られています。これは、苗字が変わることに対する、お子さま方への配慮もあることですので、フスクフダが沖縄のしきたりのジンブン(知恵)として、是正の上でも重用されている所以なのでしょう。
Sさんには、前述のように、フスクフダが必ずしもウグヮンブスクにつながることにはなり得ませんので、プラスに受け止めていただき、今年はユンヂチでもありますし、ご家族・ご親族とご相談の上、ご寺院や仏壇仏具店の専門家へ読みやすい、記入ミスのないトートーメーのお札の書き換えをご検討されてみるのも一案かと思います。