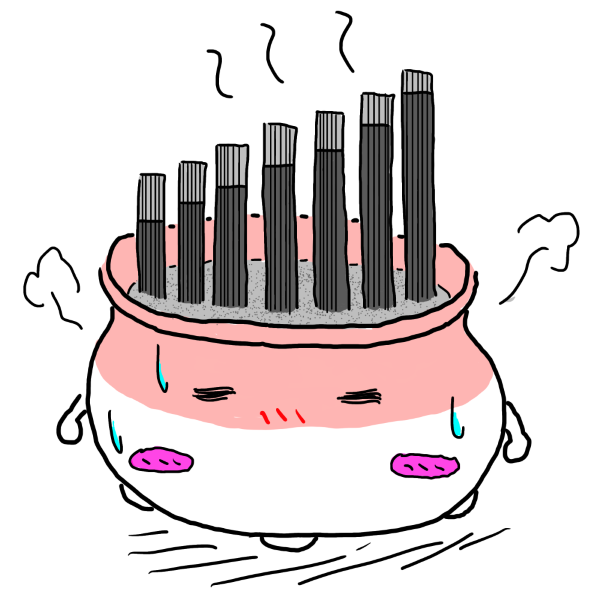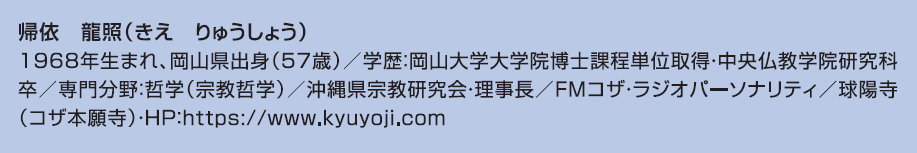琉球・沖縄年中行事 なんでもQ&A ヒヌカンのナナハシ(七橋)

週刊かふう2025年11月14日号に掲載された内容です。
トートーメーの『ウタチアギ(お焚き上げ)』
Q:友達のヒヌカンのウコール(香炉)は大きく立派で、ウグヮンブトゥチのとき、見事なナナハシができます。
わが家は「ヒンスーコール(貧乏香炉)だから」と義母から言われ、直径10センチもないウコールは、ヒラウコー15本・7組を天に昇る階段にして焼香しようとすると入りきらないどころか、火の粉が台所に充満。
やがて火事になると思います。とっても悔しいので、友達には「私もナナハシできるよ!」と噓をついて見えを張っていますが、小さいヒヌカンのウコールの皆さんはナナハシできないとき、ウコールを大きくしているのでしょうか? ナイチ線香に切り替えているのでしょうか?(中城村・Hさん・40代)
A:皆さんができることができないときのお気持ち、ナイチャームークの私なりにも思い当たるところがあります。そう、見えも張りたくなりますよね。
あらためて考えてみると、沖縄のヒヌカンのウコールは、特大・大・中・小・極小と何種類もあるので、ナナハシできるサイズもあれば、できないサイズもあるはずです。琉球・沖縄のしきたりには、「できる人用のしきたり」もあれば「できない人用のしきたり」もあり、両極端が存在する地域性・家庭性・個人性の宝庫ですので、Hさん、ご安心ください。きっとお悩みの解決方法があるはずです。ここは先人のジンブン(知恵)を尋ねてみましょう。
ナナハシとは・基礎編
Hさんは、琉球・沖縄のしきたりをとても勉強されている印象を受けます。といいますのも、ナナハシという表現は、かなりの専門用語だからです。
年中行事の旧暦12月24日(2026年は2月11日)のウグヮンブトゥチ(御願解き)では、1年間、わが家を見守ってくださったヒヌカン、正式にはミーヒヌカンガナシーメー(御火之神加那志前)が高上玉皇大帝(こうじょうぎょくこうたいてい:中国道教の最高神)のもとへお戻りになる(上天)ことから、天に昇る道標(みちしるべ)として、ヒラウコーを階段のように焼香するしきたりがあります。
また、旧暦1月4日(2026年2月20日)のヒヌカンウンケー(火之神お迎え)では、わが家へヒヌカンをお迎えする(下天)ことから、ウグヮンブトゥチの逆階段で焼香するしきたりがあります。いずれも階段の数が7段あるので、この焼香方法をナナハシ(七つの橋渡し)といいますが、シチウミ(七つの海)・ナナミチ(七本の道)・ナナタビ(七カ所の国を越える旅)など、ユタの先生曰く「言ったもん勝ち!」の傾向が垣間見え、この点でも琉球・沖縄のしきたりの寛容さであり、素晴らしさを学ぶことができます。
ナナハシとは・応用編
さて、焼香ですが、15本・7組で実践するとき、ウコールに入り切れれば問題ありませんが、入りきれないとき、Hさんがおっしゃるように、ウコールを大きくすることも、ヤマトゥウコー(1本線香)を使用することも一案でしょう。でも、Hさんのお言葉をお借りするなら、これってちょっと悔しいじゃないですか?
このナナハシは同時に焼香することが好ましいと思われがちですが、地域・家庭によっては、ヒヌカンウトゥーシ(火之神お通し)という、15本・7組を同時に焼香するしきたりもあれば、15本・1組目が燃え終わる直前に次の2組目を燃やし、2組目が燃え終わる直前に、また次の3組目を燃やす、コーブン(香分)という、ヒラウコーの燃え具合を見つつ、ヒヌカンが一段一段、確実に階段を上ったり下ったりを確認する焼香方法が、琉球・沖縄のしきたりには言い伝えられています。
今回のご回答として、ウコールが直径10センチ未満でも全然大丈夫です。最初に15本・1組目を焼香し、順次7組目まで焼香する、これでもナナハシに変わりありませんので、ぜひ、実践していただき、来年のウグヮンブトゥチをありがたくお敬いしていただければと思います。
Hさん、沖縄のヒヌカンには、ヒンスームンのヒンスーコールはいないそうで、みなさん、週刊カフウと一緒の「カフウムン・クヮフームン(果報者・幸福者)」のカフウウコールとのこと。その幸せを分けていただくありがたい年中行事がウグヮブトゥチ・ヒヌカンウンケーですので、お義母さまとご一緒に、小さなヒヌカンから大きな幸せを授かってください。