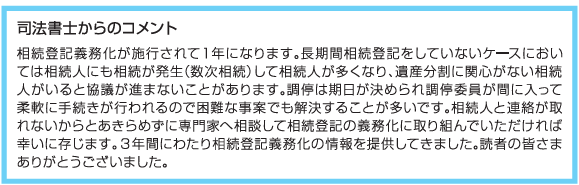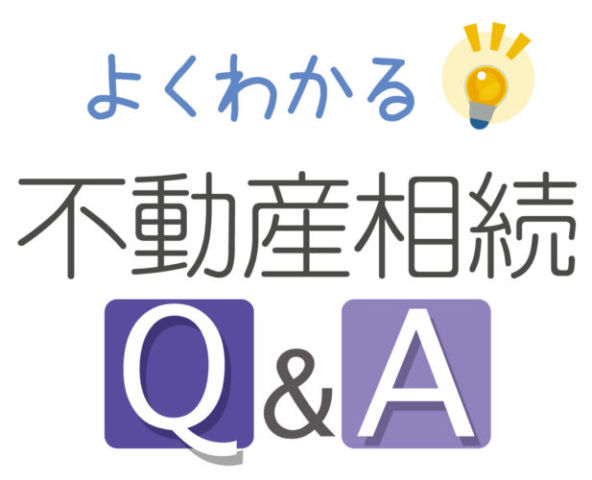新着 不動産相続Q&A File.38「遺産分割調停」について

週刊かふう2025年3月28日号に掲載された内容です。
「遺産分割調停」について
不動産相続について司法書士の経験と目線から実践的なアドバイスや解決策を提供します。今回は、中立公正な立場で当事者の意見を調整する「遺産分割調停」について、区長と青年会会長のユンタクで解説します。
【青年会会長(以下、青年会)】 3年間ユンタクしてきたこのコーナーも今回で最終回になりますね。
【区長】そうだね。毎月ユンタクしてきた甲斐あって区民にも少しは「相続登記義務化」が浸透しているような気がするな。
【青年会】ホントに勉強になりました。「遺言書」「共有」「遺産分割」などの漢字も読めて意味もわかるようになりました。ところで“区長さん”、昨年4月に義務化になって相続登記件数が増えてきているようですよ。
【区長】3年間で初めて「さん付け」で呼ばれたよ。相続登記の件数が増えたことは喜ばしいことだな。義務化は3年以内に相続登記の申請をすることを定めている。過去に相続が発生して長期間相続登記をしていない相続人は令和9年3月31日までに相続登記をしなければならない。引き続き区民にも早めの相続登記申請を勧めていくよ。
【青年会】区長~、最終回は「遺産分割調停」について教えてもらえませんか。どうしても遺産分割協議がうまくいかない友人から相談を受けているんです。
【区長】 調停手続きは家庭裁判所で行われる手続きだが、相続人間で話し合い遺産分割をすることに変わりはない。それでも、調停員2名が入って話し合いをリードしていくので感情的な対立があったとしても話し合いがまとまる可能性は高くなるようだ。どうしても協議がスムーズにいかない場合は、義務化を守るためにも調停の活用を広めてもらいたい。
【青年会】調停手続きの仕組みはどうなっているのですか。
【区長】 調停手続きは裁判官と調停委員2名(男性と女性のペア)が公正中立な立場で相続人の言い分を聞いて調整や具体的な解決案を提案したりして円満な解決を目指す手続きだ。希望をすれば調停手続き中は相続人間で顔を合わすことなく、相互に調停室に入って調停委員に言い分を伝えたり相手方の言い分を聞いたりして進めることができる。調停期日はおおよそ月に1回のペースで開かれ、申立人以外の相続人は毎回出席しなくても開くことができる。
【青年会】顔を合わせることなく手続きが進められるのはいいですね。調停委員がいることで冷静に話し合いができそうですし。
【区長】 確かに調停委員が話し合いの方向性を整理しながらリードしてくれ、かつ相手方の言い分も冷静に聞けることで誤解が解けたりして納得のいく解決も多いようだ。話し合いが成立しない場合は自動的に審判になり、審判になると裁判官が法律に基づいて決めることになる。調停で法律の取り分より多くの主張をしている相続人も審判で不利になる可能性があることがわかれば譲歩することにつながるようだ。
【青年会】調停は裁判所での手続きなので世間体を気にしそうですが……
【区長 】調停手続きは調停室(会議室)において非公開で行われるので内容が外に漏れる心配はない。実際に調停の件数は増えており多くの人が利用して解決している。調停は裁判所での遺産分割の話し合いで相続人全員の合意が必要であるが、相続人の中には無関心な人も少なくなく、遺産分割協議が進まないこともある。その場合、調停に参加しない相続人に対して「調停に代わる審判」という手続きで遺産分割調停を成立させることもあるようだ。相続登記義務化を達成させるためにも遺産分割調停を積極的に活用してもらいたいものだ。
最後に「こーみんくわんよりお知らせします🎤。相続登記をしていない区民の皆さまは令和9年3月31日までに手続きをお願いします」区長からのお知らせでした📢