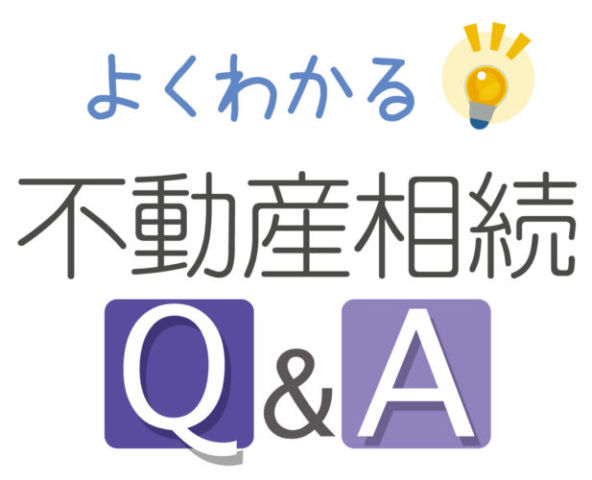基礎からわかる相続Q&A SEASON4 File.8 「所有者不明土地」について

週刊かふう2025年8月15日号に掲載された内容です。
Q.
亡くなった両親の遺産として、兄弟で実家や預金、アパートを相続することになりました。アパートは父名義の建物ですが、土地は所有者不明の借地です。所有者不明の土地とはどのような状態なのでしょうか。その土地を買い取ることはできないものでしょうか。
昨年、両親が亡くなり、私たち兄弟が両親の遺産を相続することになりました。両親は実家と預金の他にアパートを遺産として残してくれており、私たち兄弟で遺産の分配について話し合いをしているところです。
ところが、遺産となるアパートについては、建物こそ父の所有ですが、土地は父の名義ではなく、借地上に建てられているものでした。父が誰から土地を借りているのか調べてみると、所有者不明とのことで、父は沖縄県に賃料を支払っていたようでした。
所有者不明の土地とはどのような状態なのでしょうか。今後も私たちがアパートを相続して土地を使っていくことができるのでしょうか。また、父のアパートが建ってから長い年月が経っていることもあり、その土地を買い取ることはできないものでしょうか。
A.
沖縄では戦争により土地記録が焼失し、令和4年度末時点で所有者不明の土地が2690筆あります。他県では登記簿に手がかりがない土地も多い中、沖縄では琉球政府が管理し、復帰後は県や市町村が引き継ぎました。令和5年の民法改正で、こうした土地に対応する新たな制度が創設されました。その概要について見ていきましょう。
沖縄県には、先の沖縄戦による土地関係記録の焼失等によって、誰がその土地の所有者かわからなくなってしまった「所有者不明土地」が多くあり、沖縄県または県内市町村が管理をしています。
この運用は、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律に基づくもので、他都道府県とは異なる運用となっています。登記簿には通常所有者が記載されますが、沖縄県の所有者不明土地については管理者名のみが記載されています。
沖縄県等の管理者は、土地の処分はできませんが、相当と考えられる賃料を設定しての賃貸借契約を締結することができます。
今回の場合は、沖縄県が土地の管理者として相談者のお父さまらと賃貸借契約を締結していた状態です。この賃貸借契約も有効ですから、引き続き賃貸借契約に従って土地を利用することが可能です。もっとも、仮に真の所有者を名乗る方が現れ、管理者を相手に所有権確認訴訟を提起して認容判決が出た場合には、その方の所有権が認められ、賃貸借契約の対抗可否が問題となる可能性があります。
ただし、戦後75年以上が経過しており、実際にそのような主張がなされる可能性は現実的には考え難いでしょう。さらに、相談者のお父さまらが長年にわたり当該土地を利用してきた経緯もあることから、相談者のように正式に土地の所有権を取得したいと考える方もいらっしゃいます。そのような場合には、令和5年4月1日の民法改正で創設された「所有者不明土地管理人」の制度の利用が検討されます。この制度では、民法上の所有者不明土地管理人に土地の管理権限が与えられ、さらに裁判所の許可を得ることで、その土地を処分(売却)することも可能となっています。つまり、所有者不明土地管理人から、正当な手続を経て土地を買い取ることができる仕組みとなっています。
民法上の所有者不明土地管理人を選任してもらうためには、利害関係人が裁判所に所有者不明土地管理人による管理を請求することになります(民法264条の2)。無事に所有者不明土地管理人が選任されましたら、鑑定等によって土地の適正価格を示す資料を提出して所有者不明土地管理人と交渉し、土地の売買契約内容をつめた後、裁判所の許可が出れば土地を購入できるという流れとなります。
このように、「所有者不明土地」について民法上の「所有者不明土地管理人」の制度を利用して購入することが考えられます。気になる方は、弁護士に相談することをお勧めします。

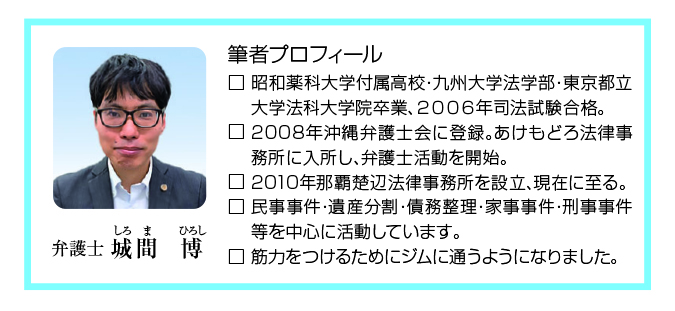
那覇楚辺法律事務所:〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺1-5-8 1階左 Tel:098-854-5320 Fax:098-854-5323