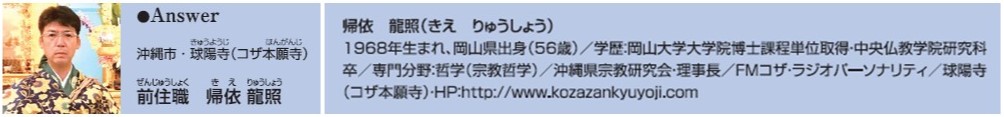琉球・沖縄年中行事 なんでもQ&A 家のしきたり、どうしてる?

週刊かふう2025年1月10日号に掲載された内容です。
火災報知器とウチカビ
Q:ジュールクニチー(十六日祭)などでウチカビを燃やすとき、わが家は仏間に火災報知器があるので、ほぼ4、5回に1回の割合で鳴ってしまいます。皆さんはどのように対処しているのでしょうか?(石垣市・Kさん・50代)
A:全国的に、神社仏閣でも線香やロウソクから出火し、全焼する事例が後を絶ちません。火災報知器の設置は義務ですので、当院でも各部屋に設置しています。
ちなみに、当院は伽藍(がらん・お寺の建物)・境内(けいだい)での火気厳禁・禁煙に努めており、火をあつかう焼香をご遠慮いただき、炉に火種を入れず抹香のみを入れる献香、しまくとぅばでいうところのカラウコー(空御香)・ヒジュルウコー(冷御香)を奨励させていただいています。
沖縄では、地域で共有するウグヮンジョ(御拝所)・ウタキ(御嶽)・ウブガー(産湯井泉)などでは、プライベートなご自宅のお仏壇やヒヌカンと異なり、ヒラウコー・線香・ロウソクを点火しないままお供えするカラウコー・ヒジュルウコーのしきたり(マナー)が言い伝えられています。
沖縄のしきたりに詳しい方々は、屋内のニバンジャー(二番座)という仏間でカビアンジをせず、屋内の仏間に準ずる屋外のナカジン(中陣・玄関先または門前)でカビアンジすることもあるようです。
これは、ウグヮンスヌグソーヌニジリ(仏壇の後生の右・お仏壇に向かって左側)という、本来カビアンジを行う場所と、ナカジンヌジーチヌカンヌニジリ(中陣の土地の神様の右・玄関先または門前に向かって左側)を同じく大切な場所と見なし、火災報知器のある屋内で行うべきものを火災報知器のない屋外で代用するジンブン(知恵)に他なりません。
沖縄の年中行事などでよくいう、「煙が出るから、カビアンジは外でやりましょうね~!」とのお言葉は、この屋内・屋外を同等とするしきたりあってのことなのでしょう。
Kさんへのご回答としましては、火災報知器を鳴らさないために、最初からカビアンジしないという選択肢(ただし、カビアンジしないと、ウヤファーフジがヒンスームン〈貧乏者〉になるとのご意見もあるようです)もありますが、ジンブンに従って屋内ではなく、同じく大切な場所の屋外の玄関先、または門前に向かって左側(地域・家庭によっては右側)でのカビアンジをお勧めさせていただきます。
※献香は、『お香を献げ奉る』との意味から、焼香を含むこともあります。
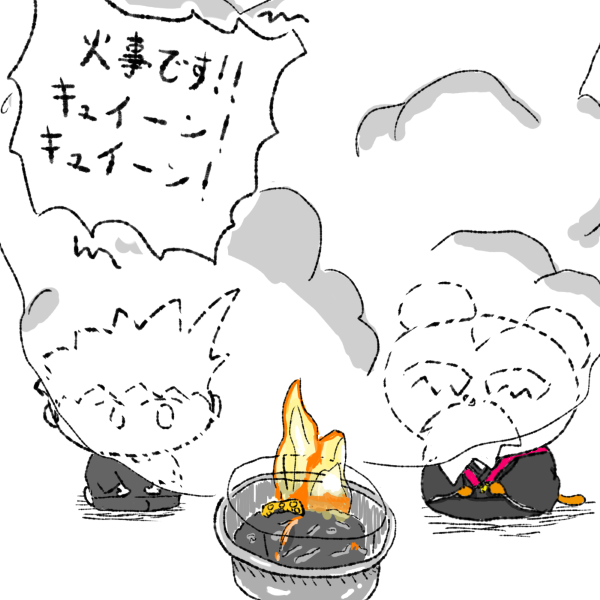
花瓶の置き方
実家の仏壇の花瓶は正面向き、嫁ぎ先は左右が内側向き、母・義母どちらも花瓶の置き方にはこだわりがあるようです。本当はどちらが正しいのでしょうか?(南城市・Tさん・40代)
Tさんからの花瓶のご質問、実はどちらも沖縄のしきたりであり、どちらも甲乙つけがたいものと言われています。一般的には、ご実家の正面向きが多いかと思います。このとき、『金華(きんか)』・『蓮華(れんげ)』という『金色の花』が真正面に向くことがポイントとなります。
一方、嫁ぎ先の花瓶の置き方は、『内絞り(うちしぼり・中回し)』という沖縄のしきたりの一つです。これは、お参りする方々がお仏壇の中央に座ることを考慮したもので、花瓶を真正面に向けると、見た目の錯覚で、生花・チャーギ・クロトンなどが外側にズレて真正面に向いていないように感じることから、意図的に左右の花瓶をお参りする方々の方向(内側)へ少しだけ回転させ、あるべくお仏壇のウカザイ(お飾り)を心がけるものです。
この『内絞り(中回し)』のしきたりは、花瓶の耳という取っ手を少しだけ内回転させることにより見た目の錯覚を逆利用する、沖縄のしきたりのジンブンであると言われています。
Tさんへのご回答として、ご実家では花瓶を真正面に向け、嫁ぎ先では『内絞り』されるよう、ケースバイケースのウカザイを心がけていただければと思います。
ご両家のお母さま・お義母さまともども、沖縄のしきたりを大切にされていることは、Tさんにとって、大変ありがたいことかと存じます。