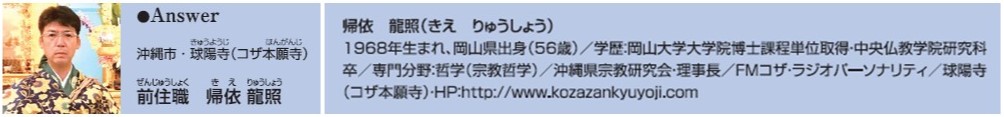琉球・沖縄年中行事 なんでもQ&A ウサギムンの数と量

週刊かふう2025年2月14日号に掲載された内容です。
ウサギムンの数と量
Q:この歳になり、今さら聞けないことですが、沖縄のウサギムンには、準備する数と量があるような気がします。長男の嫁にちゃんとした沖縄のしきたりを教えたいので、代表的なものを簡単にまとめてください(那覇市・Tさん・80代)
A:Tさんのおっしゃる通り、沖縄のしきたりの中、ウサギムン(お供え物・供物)には、お供えする数と量について、地域ごと、家庭ごとに暗黙のうちのルールがあるといわれています。
ミンナリーチチナリー(見習い聞き習い)という独自の学習方法も素晴らしいことですが、私の副たる専門分野『琉球・沖縄学』より、『数理的作法・心得』として、数と量について簡単にまとめさせていただきたいと思います(その根拠には、諸説あることをご理解ください)。
<重箱>
●タジューバコ・チュクン(重箱4箱:お餅2箱・おかず2箱)
重箱2箱(お餅1箱・おかず1箱)をご法事に当たるウヤファーフジへのウサギムンとし、別の重箱2箱をご法事に当たらないウヤファーフジへのウサギムンとする考え方。また、重箱2箱をイチミ(生きている者)からグソー(死後の世)へのウサギムンとし、別の重箱2箱をグソーからイチミへのウサンデーとする考え方など。
●チュジューバコ・ハンクン(重箱2箱:お餅1箱・おかず1箱)
お餅1箱をご飯と見立て、ご飯・おかずで1食分の配膳とする考え方。また、タジューバコ・チュクンを食べ残してしまうことを考慮し、重箱をウサンデーする人数に応じてコンパクトにする考え方など。
<箸>
●ユジンバシ(四膳箸)
タジューバコ・チュクンのとき、それぞれ4箱の重箱にお箸をお供えする考え方など。
●タジンバシ(二膳箸)
チュジューバコ・ハンクンのとき、お餅とおかずの重箱に1本ずつお箸をお供えする考え方。また、お餅の重箱はお箸にお餅がくっついてしまうので、2箱のおかずの重箱のみにお箸をお供えする考え方など。
●グソーバシ(位牌人数分箸)
トートーメーのウヤファーフジの人数に合わせ、お箸をお供えする考え方など。1名でしたらチュジンバシ(1膳箸)、10名でしたらトージンバシ(10膳箸)。このトージンバシのレベルになりましたら、10膳20本のお箸を輪ゴムでクビっていますね。
●塗り箸・竹箸
お仏壇などの屋内の重箱では、ウヤファーフジの生前の日常を再現するため、愛用の塗り箸・竹箸をお供えする考え方など。
●割り箸
お墓・ウガンジョ(御拝所)・カー(井泉)などの屋外では、重箱にお供えした塗り箸・竹箸にマジムン・ヤナムンがくっついてこないよう、廃棄できる割り箸をお供えする考え方など。
<ウチャトー(御茶湯)・サキ(酒)>
●5杯(ウチャトー茶碗2杯・コップ3杯)
ウチャトー茶碗2杯にそれぞれお茶を入れ、コップ3杯にお白湯(お水)2杯・お酒1杯を入れ、トートーメーにお供えする考え方など。1台のトートーメーに対し、一番多いウチャトー・サキのお供え方法となります。
●4杯(ウチャトー茶碗2杯・コップ2杯)
ウチャトー茶碗2杯にそれぞれお茶を入れ、コップ2杯にお白湯(お水)1杯・お酒1杯を入れ、トートーメーにお供えする考え方など。
●3杯(ウチャトー茶碗2杯・コップ1杯)
ウチャトー茶碗の右側にお茶、左側にお白湯(お水)を入れ、コップ1杯にお酒を入れ、トートーメーにお供えする考え方など。
●2杯(ウチャトー茶碗2杯)
ウチャトー茶碗の右側にお茶、左側にお白湯(お水)を入れ、お酒を省略してお供えする考え方など。
●半分チャー
ウチャトー茶碗とコップにお茶・お白湯(お水)・お酒を半分ほど入れ、イチミからは半分、不足分の半分はグソーから注ぎ足してくださいとお供えする考え方など。
●グソーチャー
ウチャトー茶碗とコップにお茶・お白湯(お水)・お酒を70パーセントほど入れる。イチミからグソーへのトータビ(唐旅・遠旅)が7つの川を越え、7つの山を越える、ナンカ(七日)・七七(四十九日)であることから、数字の7を尊み、ウチャトー・サキも7をお敬いするお供えの考え方など。
70パーセントの目安として、とあるユタの先生は、「ウチャトー茶碗の半分の上の半分くらい入れなさい」とよくおっしゃっておられました。これでいきますと、厳密には、半分=50パーセントと上の半分=25パーセントですので、合計75パーセントくらいになってしまうのですが、「大丈夫、余るくらいが上等さ~!」と御願不足にならないことを笑顔でご説明されていました。
Tさん、仮にこちらに該当しないウサギムンの数と量がありましても、それは沖縄のしきたりの地域性・家庭性ですので、今後とも、無理のない範囲で、ご参考になさっていただければと存じます。