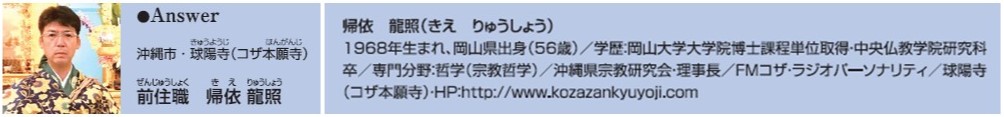琉球・沖縄年中行事 なんでもQ&A 旧盆のウチカビ(カビアンジ)

週刊かふう2025年8月8日号に掲載された内容です。
Q:わが家の旧盆のウークイは、翌日にまたぐため、高齢のおじさん・おばさんたちは、「ニッヴァットー(おやすみなさい)」とお仏壇にご挨拶して、早々に帰ります。カビアンジは、本人が燃やさないと通らないそうですが、今年も私たちが、おじさん・おばさんたちのウチカビを勝手に燃やして大丈夫でしょうか?(宮古島市・Yさん・ 50代)
A:Yさん、沖縄のしきたりを大切にする、宮古島あるあるのご相談ですね。私も、大きな盥(たらい)をカニバーキ(ウチカビを炙る祭具のこと。沖縄本島では、カビアンジャー)に見立て、火柱が立つほど、大量のウチカビを炙られている光景を目にしたことがあります。ウチカビを炙ることをカビアンジなどと言いますが、誰がウチカビを炙るのかは、地域・家庭により、それぞれの考え方があるようです。この点、宮古島のしきたりも参考にしつつ、先人のジンブン(知恵)を訪ねていきましょう。
喪主・施主のカビアンジ
沖縄では、ウサギムン(お供え物)をウサンデー(お下げ)するとき、ウサンデーしたときに生じる不足分を金銭的に補うため、グソーのお金であるウチカビをカビアンジすることが知られています。このとき、誰がカビアンジするのかは、儀式・法要の責任者である、喪主・施主が行われることが多いようです。
喪主・施主がカビアンジする理由には、諸説ありますが、喪主・施主は、儀式・法要の最後まで残ることが多いことから、今回のご相談のように、早く帰りたいご親族に対し、「私が代表でウチカビを炙りますから、みなさんは早く帰っても大丈夫ですよ」などのお気遣い・ご配慮が垣間見えます。
一方、Yさんのおっしゃる「ウチカビは、本人が燃やさないと通らない」とのご意見もしかり、このようなとき、沖縄のしきたりには、『ナーヌイン(名乗り)』という是正方法があると言い伝えられています。
『ナーヌイン』とは?
『ナーヌイン』とは、『名乗り』と訳し、『お名前を申し上げる』との意味になります。その語源は、私が専門とする仏教学(真宗学)にちなむといいますから、個人的には驚きに他なりません。
旧盆などで演舞されるエイサーのフェーシ(囃子)の中に、『ナミアミダビチ・アミダビチ(南無阿弥陀仏・阿弥陀仏)』があります。この『南無阿弥陀仏』のことを専門用語では、『名号(みょうごう、旧漢字では名號と書きます)』といい、『旧漢字の名號の通り、虎のように大きな声で仏様のお名前を申し上げる』→『名乗り→称名(しょうみょう)』と訳されます(『名乗り』は、「私があなたを必ず救います」との仏様から私たちに対しての『名乗り→招喚(しょうかん)』も意味しています)。
『名乗り』は、自らの存在を知らしめ、相手に安心感を与えるのみならず、仏様(沖縄では、ウヤファーフジ)と人、グショウ(仏様の世界のこと。沖縄本島では、グソー)とナカビ(私たちの世界のこと。沖縄本島では、イチミ)の大切なコミュニケーションにもつながるとの深い意味合いがあります。
この『ナーヌイン』は、喪主・施主が、ウチカビをお供えされた方々のお名前を申し上げ(名乗り)つつ、代理として炙るときにも応用されています。また、『ナーヌイン』は、『お名前を申し上げる』だけでなく、ウチカビの上にシルカビ(半紙)を置き、そこにお供えした方々の『お名前を書き上げる』ことも含むといいます。
今回、Yさんへのご回答として、この『ナーヌイン・カビアンジ』を応用されてみてはいかがでしょうか? お供えされたご本人がお帰りになる前、直々にご自分のお名前を書いていただければこの上ありません。この書き上げたウチカビを喪主・施主が代理でカビンアンジすることにより、直接お供えされたご本人がカビアンジしたことになるといいます。
宮古島では、サス(神女)の先生が、「『トートゥイ(尊い、感謝・合掌のこと。沖縄本島では、ティーウサー・ウートートゥ)』とお香を額に頂戴しながら、ブツダン(お仏壇)にご焼香されているお姿を拝見したことがあります。私は、この『トートゥイ』とおっしゃる宮古島のしきたりが大変ありがたく、Yさんにもぜひ、『トートゥイ』とウチカビを敬いながら、今年の旧盆・ウークイをご供養いただければ幸いです。