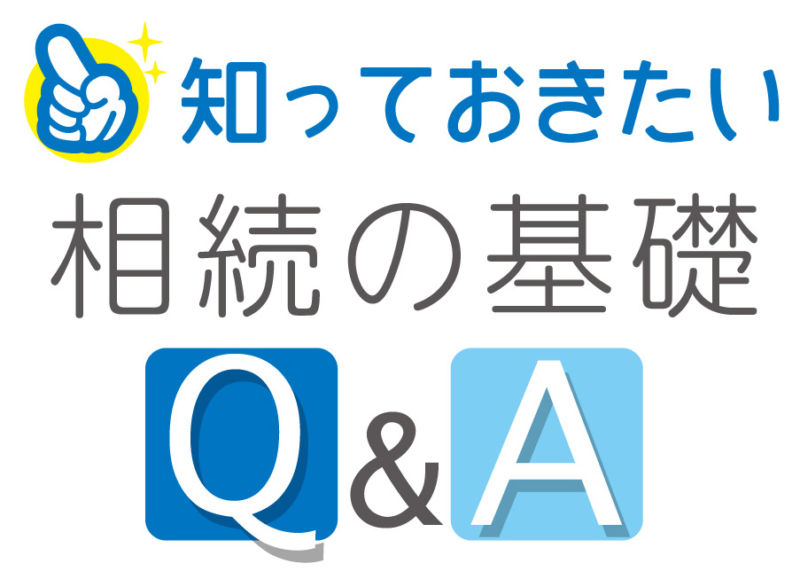基礎からわかる相続Q&A SEASON4 File.10 民事信託と信託監督人
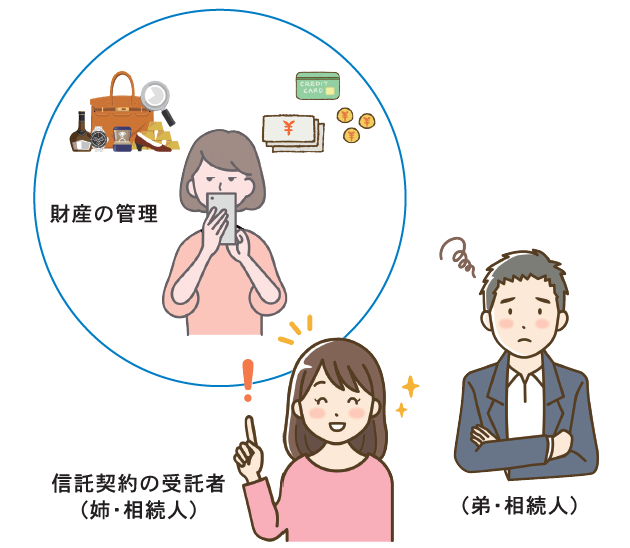
週刊かふう2025年10月17日号に掲載された内容です。
Q.
夫から相続した自宅で一人暮らしをしていますが、体力の衰えを感じ将来は介護施設への入所を検討中です。費用は自宅売却で賄う予定ですが、判断能力の低下により売却できなくなることを懸念しています。娘と息子の関係が悪く、娘に財産管理を任せると息子が不利になるのではと心配しており、公平性を保ちつつ将来に備える手段を模索しています。
私は現在夫に先立たれ、夫から相続した家で一人暮らしをしています。現在は近くに住んでいる娘のサポートもありなんとか一人暮らしができていますが、だんだん体力の衰えを感じてきており、将来的には介護施設への入所を考えています。私としては、この施設への入所費用等の今後の費用は、今住んでいる家を売却して工面しようと思っています。
ただ、私は最近物忘れが出てきて、施設入所が必要になった際に、私の判断能力が落ちて自宅を売却することができないのではないか心配しています。私には娘の他に息子もいるのですが、娘と息子は最近折り合いが悪く、私としては娘と息子は平等に扱いたいので、娘に財産を任せることで息子が不利になってしまわないかも気がかりです。このような状況で、私の判断能力が落ちてしまうことに備える対応として、どのような手段が考えられますか。
A.
判断能力等が衰えた場合に備えてとりうる選択肢として、信託契約があります。信託契約を利用することで、信託目的のために信託財産の管理や処分を委託者に行ってもらうことができます。「民事信託」には成年後見と違って家庭裁判所による監督がありませんので、その点で不安を感じる方もいるかもしれませんが、「信託監督人」の制度を利用して信託目的の実現を図ることが考えられます。
相談者のケースですと、娘さんが将来のご自宅売却や売却代金の管理等を引き受けてくれるのであれば、相談者を「委託者兼受益者」、娘さんを「受託者」とする「信託契約」を締結することが考えられます。
信託契約とは、委託者が所有する財産を受託者に移転し、信託目的に従って受託者にその財産の管理または処分をさせる契約のことです。本件では、相談者と娘さんとの間で信託契約を締結した場合、娘さんが信託目的に従って
信託財産とした不動産や金銭の管理処分等を行うことになります。
一方で、信託契約を締結していない場合、相談者本人が判断に力を失い、自らの意思に基づいて売買契約を締結することが難しくなってしまうと、相談者名義の居住用不動産を処分するには、まず成年後見の申立てを行い、家庭裁判所が成年後見人を選任したうえで、その成年後見人が家庭裁判所に「権限外行為の許可」を申請し、許可を得る必要があります。
信託契約を締結した受託者は、信託の目的にしたがって信託財産の管理処分をしなければならないとされますが、ご家族を受託者に選んでいても、必ずしも適切に財産を管理してもらえるとは限りません。相談者の場合ですと、娘さんが不適切な財産管理を行ってしまうと相続の場面で息子さんの取得分が減ってしまう可能性があります。
信託目的にしたがった管理処分がなされるかどうかについて不安があるのであれば、信託契約において、帳簿作成義務を明記した上で、弁護士等を信託監督人として指定することが考えられます。
信託監督人とは、信託契約で定められた通り信託が行われているかどうかを監督する者です。信託監督人が定期的に帳簿や証憑(しょうひょう)書類を確認することで、信託目的にしたがった信託の実現や、他の利害関係人の権利保全に資することにつながります。
弁護士会では、信託監督人の活用を推奨する研修も行っています。そのため、信託監督人の設置を検討される場合は、信託契約書の作成とあわせて、弁護士に信託監督人を依頼することをお勧めします。
また、信託契約では、委託者が亡くなった際の信託財産の帰属先をあらかじめ指定することも可能です。ただし、その内容が相続人の遺留分を侵害してしまうと、後に紛争が生じるおそれがありますので、十分に注意が必要です。

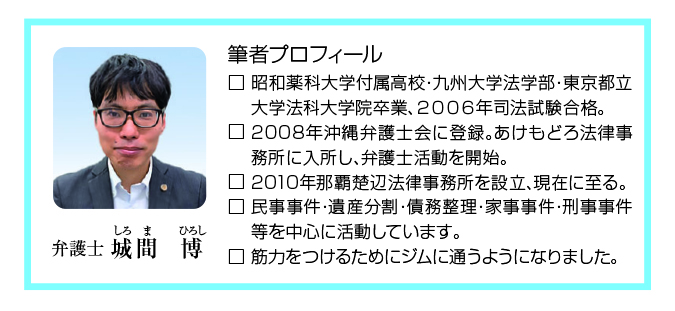
那覇楚辺法律事務所:〒900-0023 沖縄県那覇市楚辺1-5-8 1階左 Tel:098-854-5320 Fax:098-854-5323