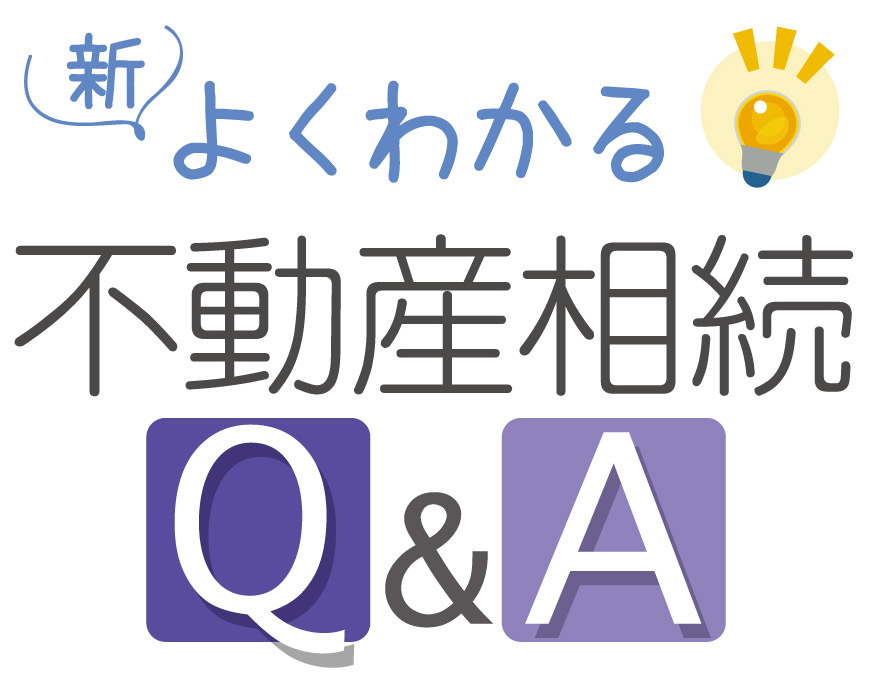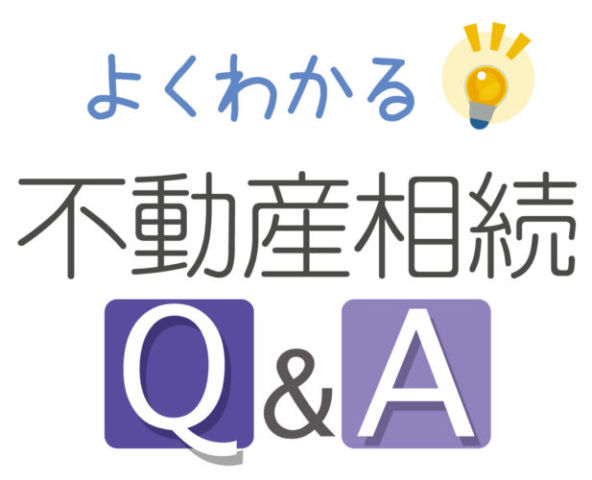新 よくわかる不動産相続Q&A File.12
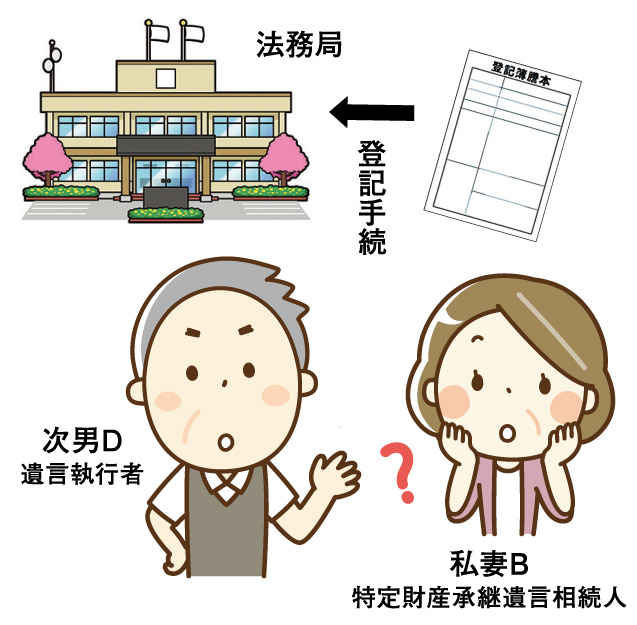
週刊かふう2019年12月20日号に掲載された内容です。
特定財産承継遺言がなされた場合の遺言執行者の権限について
改正相続法では、特定財産承継遺言がなされた場合の遺言執行者の権限を明文化しました。
これは、遺言執行者が特定財産を承継する受益相続人のために対抗要件を備えることができるとしたもので、高齢化が進む現代社会において、遺言執行者の存在がますます重要になってきたことを示すものでもあります。
Q.私妻B(70歳)は、46年間連れ添った夫A(75歳)との間に長男C(45歳)・次男D(43歳)がおりますが、その夫Aが最近亡くなりました。
夫Aの遺産としては、築30年の2階建ての自宅(土地建物、土地は約2000万円・建物は約1000万円の価値)があるのみです。夫Aは、その土地建物を私妻Bに承継させる旨の遺言を残してくれました。更に、長男Cが事業の失敗で相当の負債を抱えており、その土地建物を処分する可能性があることを考慮して、次男Dを遺言執行者と指名したようです。
私妻Bは登記手続きには詳しくありません。その登記手続きを遺言執行者の次男Dが取ってくれるのでしょうか。教えてください。
A.特定の財産を1人または数人の相続人に承継させる旨の遺言を特定財産承継遺言といいます。
従前から利用されている特定の財産を相続人に「相続させる」旨の遺言も、この特定財産承継遺言にあたります。最高裁は、特定財産承継遺言では特定財産を承継した受益相続人が単独で登記申請をすることができるから、当該不動産がいまだ被相続人名義にある限り遺言執行者の職務は顕在化せず、遺言執行者は登記手続きをなすべき権利・義務を有しないと判示しました(最高裁平成11年12月16日)。この最高裁判例の立場から、本件では、妻Bは単独で本件土地建物の登記申請手続きができるから、その登記名義が亡夫Aにある限り、次男Dが遺言執行者といえども亡夫Aから妻Bへの移転登記申請手続きを取ることはできないということになります。しかし、これでは高齢で登記手続きに通じない妻Bの正当な利益が害される危険性があります。
しかも、9月27日号でも説明したとおり、改正相続法の下では、取引の動的安全確保の見地から、仮に妻Bが登記申請手続きを取らない間に、長男Cが資金を得ることを目的として本件土地建物の相続持分1/4を自己名義にし、その持分1/4を第三者Eに売却し、第三者Eが登記を備えるに至った場合には、妻Bは、登記無くしてその持分1/4を第三者Eに対抗することはできません(民法899条の2第1項)。妻Bの正当な利益確保の見地から、妻Bに速やかに対抗要件たる登記を備えさせる必要があります。
そこで改正相続法では、特定財産承継遺言がなされた場合において、遺言執行者がその遺言によって特定財産を承継する受益相続人のために対抗要件を具備させる権限を有することを明文化しました(民法1014条第2項)。これによると、遺言執行者たる次男Dは、本件土地建物について亡夫Aの最終の意思を尊重し、妻Bの正当な利益を確保するために、亡夫Aから妻Bへの移転登記手続きを取ることができることになります。
特定財産承継遺言がなされた場合の遺言執行者の権限に関する民法1014条第2項の規定は、令和元年7月1日(改正相続法施行日)以降に作成された遺言に適用されます。ご参考になさってください。
これまで6カ月12回に亘り、主として改正相続法が不動産相続に与える影響等について解説して参りましたが、今回で最終回となりました。読者の皆さまに、多少なりとも改正相続法に関する情報をご提供できたのであれば幸いです。読者の皆さま、長い間「新 よくわかる不動産相続Q&A」を読んでいただき、本当にありがとうございました。