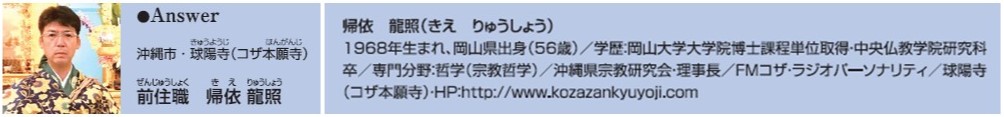琉球・沖縄年中行事 なんでもQ&A ダーグ(団子)の置き方

週刊かふう2025年5月9日号に掲載された内容です。
Q:オガミサー(拝む人)のおばさんから、「ダーグには置き方があるから気をつけなさいよ~」とアドバイスをいただきました。「どんな置き方ですか~?」と尋ねると、「だっからよ~」で話は終わってしまいました。これって気になりますよね?(南城市・Tさん・30代)
A:一見、なんでもない光景のようですが、オガミサーの先生がおっしゃる通り、ダーグの置き方に、かなりこだわる沖縄のしきたりが存在するようです。私も最初、さほど気にしていなかったのですが、知ってしまうと置き方に目がいくようになるから不思議なものです。
山積みと平置き
沖縄のお仏壇などでお供えするダーグは、おおむね、小皿に盛りつけることで知られています。しかも、県外出身の私が驚いたのは、中秋の名月で盛りつける、小高く山積みするものでなく、小皿に平置きという花のデザインのような盛りつけ方法です。雰囲気としては、小皿の中央に1個のダーグを置き、その周辺に6個のダーグを円形に配置するイメージです。
初めて拝見したとき、「このご家庭はオシャレだな……」程度の印象だったのですが、年々、ご法事などにお参りさせていただくたび、その「オシャレなご家庭」が沖縄にはわんさか存在することに気づき、ここで「オシャレなダーグ」が沖縄のしきたりであることに初めて気づきました。
ウナンカ(七日)説とウスーコー(ご法事)説
なぜ、このような置き方になるのかには諸説あるようですが、琉球料理研究家の大御所3人の先生いわく、「これには深い意味がありますよ」とご意見は一致していること自体が驚きでした。
その仰せには、ウナンカとウスーコーにより、意味合いが異なるようです。お葬式を終え、ハチナンカ(初七日)~シンジュークニチ(四十九日)までの逮夜(たいや)ともいうウナンカでは、小皿の中央にある1個のダーグをシンジュークニチと見立て、周辺の6個のダーグをハチナンカ~ムナンカ(六七日)ととらえるようです。つまり、ハチナンカを出発点と考え、毎週、大切な故人さまを敬い、7週目には中央のダーグのシンジュークニチに行きつく、しまくとぅばで言うところの『トータビ(唐旅・遠旅)』を表しているのだとか。
一方、ウスーコーでは、ナンカではハチナンカであったダーグが一周忌のダーグに変わり、2個目~6個目までのダーグを三回忌・七回忌・十三回忌・二十五回忌・三十三回忌ととらえていくのだそうです。最後の1個の中央にあるダーグをグソーというウヤファーフジの世界に見立て、一周忌~三十三回忌まで大切にご法事したら、「グソー極楽しますよ」というグソーダーグととらえていく点がとてもありがたいところです。
ティーチダーグとターチダーグ
さて、ここからがオガミサーの先生がおっしゃる、ダーグの置き方の次なるステージと申しましょうか。ティーチダーグとターチダーグというダーグの配膳方法が存在するとのことです。
詳細を申し上げれば、ティーチダーグでは、6個の円形のダーグのうち、グソーから見て手前(自分から見て奥)に1個のダーグを置き、ここをハチナンカや一周忌の出発点とする考え方のことをいいます。
ターチダーグでは、同じ場所に2個のダーグを置き、2個のうちのいずれかをハチナンカや一周忌の出発点と見なすとのことです。ただし、ターチダーグでは、この2個のうちどちらを出発点と考えるかで地域・家庭により諸説に分かれるようです。このあたりがオガミサーの先生がおっしゃる「ダーグには置き方があるから気をつけなさいよ~」というアドバイスのポイントなのかもしれません。
沖縄のしきたりに詳しい先輩方の仰せには、「ターチダーグよりティーチダーグ」というアドバイスをよく耳にいたします。これは、「諸説にわかれるターチダーグより、一説でまとまるティーチダーグ」という意味合いなのかもしれません。Tさんには、差しつかえなければ、来るウマチー(御祭)や旧盆などの年中行事にお供えするダーグでは、ターチダーグもありがたいところですが、差しつかえなければティーチダーグも心がけていただければと思います。