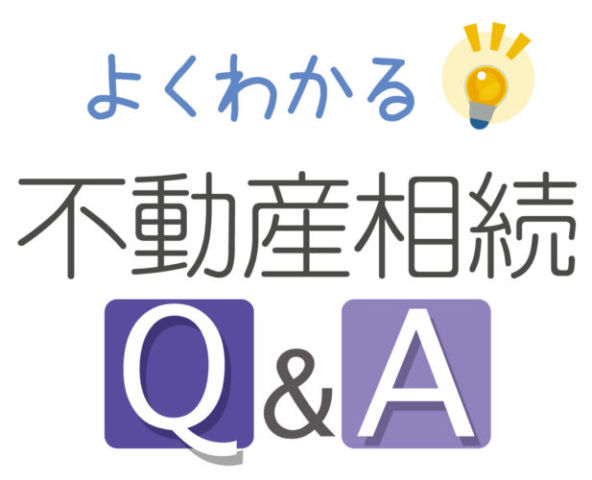新 よくわかる不動産相続Q&A File.8

週刊かふう2019年10月25日号に掲載された内容です。
相続債権者の保護について
新たな改正相続法では、相続人に対する債権者及び登記制度・強制執行制度に対する信頼保護の見地から、遺言の遺産を取得させる形態に関わらず、相続人と第三者の優劣を登記の有無によって決しようとの制度を設けましたので解説いたします。課題解決の考え方・ヒント・情報としてご活用いただけましたら幸いです。
Q.事業を営んでいる私Dは、取引先のCに対して、1500万円の債権を有しています。
最近、債務者であるCの父Aが亡くなり、長男であるCとCの母であるBが、その遺産(自宅の土地建物、土地は約2000万円・建物は約1000万円の価値)を相続したことを知りました。しかし、どうもAの遺言では、土地・建物をBに取得させる内容のようです。
私は、事業存続のために、どうしてもCに対する取引債権1500万円を回収しなければなりません。何か良い方法はないでしょうか。
A.今回は、遺言について被相続人・相続人の立場からではなく、相続人に対する債権者の立場から考えてみました。
長男C(債務者)は、遺産である本件土地・建物について、法定相続分1/2を有しています。しかし、長男Cは、父Aの本件土地・建物を母Bの取得させる旨の遺言が存在する以上、おそらく持分1/2の相続登記の手続きを取らないでしょう。そこで、長男Cに対する相続債権者Dは、利害関係人として長男Cに代位して持分1/2の相続登記の手続きを取り、その持分1/2を差し押さえて、長男Cに対する取引債権1500万円を回収する方法が考えられます。
ここで本件土地・建物をAが妻Bに取得させる遺言の形態について考えてみたいと思います。方法としては「遺贈」・「相続させる旨の遺言」による二つが考えられます。
「遺贈」による場合は、最高裁は、受遺者は、対抗要件たる登記なくして、相続債権者に不動産の遺贈を受けたことを対抗できないとしました(最高裁昭和49年4月26日判決)。この判決は債権の遺贈に関する事案の判決ですが、不動産の場合も考え方は同じです。従って、本件では、先に登記を備えたDは、妻Bに対し、持分1/2の登記及び差押は有効である旨を主張しうることになります。
これに対し、「相続させる旨の遺言」による場合は、最高裁は、相続させる旨の遺言により不動産を取得した相続人は、登記なくして第三者に不動産取得を対抗しうると判示しました(平成14年6月10日)。従って、本件では、先に登記を備えたDといえども、妻Bに対し、持分1/2の登記及び差押の有効性を主張し得ないということになります。
相続債権者Dの立場からは、Aの遺言の内容は知り得ないのが通常です。にもかかわらず、「遺贈」・「相続させる旨の遺言」いずれの方法であるかによって結論を異にするのは、遺言の有無・内容を知り得ない相続債権者等の利益を害し、登記制度・強制執行制度に対する信頼を害する危険性もあります。
そこで、改正相続法では、相続させる旨の遺言についても、法定相続分を超える部分については、登記等の対抗要件を具備しなければ、債務者・第三者に対抗することはできないとしました(民法899条2項)。これによると、「遺贈」・「相続させる旨の遺言」いずれの内容の遺言であるか問わず、先に登記を備えたDは、妻Bに対し、持分1/2の登記及び差押は有効である旨を主張しうることになります。
民法899条の2は、既に本年7月1日から施行されています。今後は、「相続させる旨の遺言」についても、登記の有無を基準として運用されることになりますので、注意する必要があるでしょう。